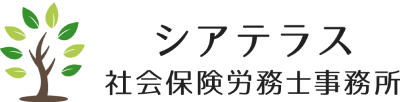20年以上前。上の娘が生まれて、復帰して、時短を取っていたころ、すみませんが口癖になっていました。
娘にアレルギーがあり、小児科・皮膚科・耳鼻科・眼科通い。
通院したり、休んだり、保育園から電話があったり、ほぼ毎日。
そのたびに職場には「すみません」。理解ある職場だったのに。
「ありがとう」より、なぜ「すみません」だったのか。
『ワーク・エンゲイジメント』(島津明人氏)の文章が、ぴったり心情に合っていました。
周りの人に親切にしているのに、周りの人は自分に親切にしてくれない場合(過少利益)はやりきれない気持ちになります。一方、周りから親切にしてもらっているのに自分が親切にできていない場合(過剰利得)は、申し訳ない気持ちになります(心理的負債の状態)
『ワーク・エンゲイジメント~ポジティブ・メンタルヘルスで活力ある毎日を』
当時の私は、職場では申し訳ない気持ちになり、家ではワンオペ状態でやりきれない気持ちになり。
どちらも偏っていました。
この文章は、「思いやりの行動」のなかのもので、
思いやり行動は、ワーク・エンゲイジを高めるために、個人ができることの1つとされます。
困ったことをちょっと聞けたり、声を掛け合ったりする思いやり行動。助け合いの輪が職場内に広がると、職場全体の風通しがよくなって、安心して仕事ができる環境につながり、
結果、ワーク・エンゲイジメントが高まり、生産性アップも期待できる、というものです。
育児や介護、両立の課題に直面したら「すみません」となるのは仕方なくて。
でも、感謝もことばにして伝えられたら、それも思いやり行動。
「お互いさま」は「互恵性」と言うそうです。