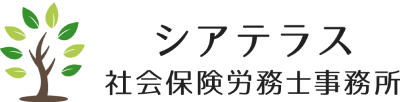子育ての時代、会社の気づきがカギに
厚生労働省の最新調査(令和6年 雇用均等基本調査)によると、男性の育児休業取得率が40.5%(令和5年は30.1%)と過去最高を記録しました。
調査の対象が、令和4年10月からの1年間に出産、育休開始した従業員。今回調査から「産後パパ育休」(令和4年10月施行)の制度利用者が含まれることも取得率アップの要因です。
実際、出産直後の8週間以内に取得できる「産後パパ育休」は、6割以上が活用したという結果になりました。
ますます共育ての時代になっていきそうです。
事業所規模別で取得率を見ると…
事業所の規模別に男性の取得率をみると、
500人以上 =53.8% 前年度比19.6ポイント上昇
100~499人=55.3% 同24.2ポイント上昇
30~99人 =35.8% 同4.4ポイント上昇
5~29人 =25.1% 同1.1ポイント低下
100人以上の企業で取得率が大幅にアップ、100人未満の事業所との開きが大きくなっています。
課題として大きいのは代替要員の確保と思われます。
1人で何役もこなす、代わりがいないという声も、両立支援でよく聞きます。
休めば誰かの負担が増える、難しいですが。
突発的に起こり得る介護や病気に比べ、育児は準備期間があることも事実。
採用力や離職率対策も意識し、BCPのように備えていくのが良いように思います。
取得しやすさのための、ちょっとした工夫
妊娠・出産の申し出があったら、制度を“個別”に案内(法改正で義務化になりました)
実際に取得した社員の体験談や声を社内で共有
取得後の職場復帰や評価への不安を減らすようなアナウンスも、安心材料になります。
まとめ 育休は、育児だけじゃなく“関係を育てる休み”
短期間でも、育休は「家族と過ごす時間」「育児への気づき」「働き方の再確認」など、多くの意味をもった時間です。
効率よく働くことへの意識づけにもつながります。
会社にとっては、業務の棚卸しやマニュアル整備のほか、属人化している業務がないか、見直しの機会にもなります。
「育休復帰プランに業務の引き継ぎを盛り込んだことで、男性従業員が詳細なマニュアルを作成したうえで休業に入りました」という話を両立支援の訪問企業で、聞いたことがあります。
男性育休が増えてから離職率が下がったそうで、企業規模30人ほどの会社さん。これからも男性を含め、育休推進に力を入れたい、と。
気持ち良く制度を利用できる、できることを尽くして休む、お互い感謝をことばにする――こうした積み重ねが社風につながって、会社と従業員の関係性も育っていくように感じた支援でした。