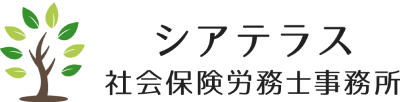タイトルは、私が両立支援の訪問支援で、時々聞かれることばです。
「(看護等休暇)有給対応までできなくて、無給で申し訳ない」とそっと話される代表者の方もいました。
25年4月の法改正もあり、改めて看護等休暇について整理してみます。
看護等休暇とは
看護等休暇は、子どもが病気やけがをしたとき、予防接種や健康診断を受けさせるときに取得できる休暇です。
25年4月から、感染症に伴う学級閉鎖、入園(入学)式、卒園式も取得できる理由に加わりました。
1人につき年5日(2人以上なら10日)まで取得でき、時間単位で取ることも可能です。
対象年齢は「小学校3年生まで」に引き上げられました。
厚生労働省の調査では、小学生になってからも医療機関を受診する頻度が高い実態が示されており、現実に即した見直しだといえるでしょう。
無給なのに意味があるの?
厚生労働省の「雇用均等基本調査(令和3年度)」によると、看護等休暇の賃金取扱いは以下の通りです。
◇有給対応:27.5%、一部有給:7.4%、無給対応:65.1%
看護等休暇の賃金支払いは法的な定めがなく、会社が任意で決めることができます。
調査結果では、6割以上の企業が無給というのが現状。私が支援した企業でも、同じ割合の印象です。
無給の休暇のため、利用が少ない、というお話も時々聞きますが、無給でも制度としての意味は大きいのです。
なぜなら。法律で保障された休暇で、取得を理由に不利益な取扱いをすることは禁止されているから(育児・介護休業法第16条の5)。無給だったとしても「休んだら評価が下がる」「不当な扱いを受ける」ことがないから、です。
企業としては、就業規則や社内通知で制度の趣旨を伝え、従業員が安心して取得できる環境を整えていただくことが重要です。
企業が確認しておきたいこと
2025年4月の法改正に対応について
1.就業規則の見直し
→ 対象年齢を「小学校3年生まで」に修正し、社員に周知
→ 入社すぐ利用できる規定になっているか確認(労使協定による継続雇用6か月未満除外規定も廃止となったため)
2.申請書・社内様式の更新
→ 「子の年齢制限」に関する文言や申請書フォーマットを変更
3.制度の周知・説明
→ 無給であっても「法律で保障された休暇」であることを、明確に伝える
→ 管理職研修などで、現場の理解を深めるのも効果的
使われる制度にするには、使いやすい雰囲気づくりが大切だと思います。
従業員にとってのメリット
看護等休暇は「いざという時の安心」でもあります。
子どもの体調で休んだと思ったら、また保育園から呼び出され、、、子どもの体調不良で有給休暇がなくなっていく、、、そんな切ない場面も多いので。
無給でも「法的に休める制度がある」というのは心理的な安心感です。
時間単位で取得できるため、「午前中だけ病院」「午後から出社」といった柔軟な働き方も可能です。
なお、看護等休暇・介護休暇の時間単位取得は、2021年1月の改正。
育児介護は法改正が多く、「時間単位」の部分が修正しきれていない会社さんも見かけますので、ご留意ください。
制度の利用しやすさは、結果的に離職防止や人材定着、採用面での好印象にもつながります。
支援をしていても、感じる想いです。
お知らせ
【法人向け 育児支援ハンドブックの作成】
両立支援の現場で寄せられる質問をもとに、「企業が自社の規則に合わせて活用できる」育児支援ハンドブックを作成しています。
看護等休暇・時短勤務・法改正対応の内容を、貴社の就業規則に合わせてカスタマイズいたします。
社内説明会や育児支援方針の共有ツールとしてもご活用いただけます。
ご関心のある方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。