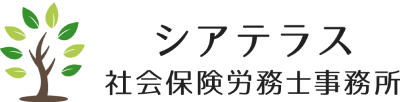2025年4月からの介護支援に関する法改正
2025年4月、介護支援に関する法改正が施行されました。
「最近、介護が必要な家族がいて…」
そんな従業員からの声、まだ身近に感じていないかもしれません。
でも、介護はある日突然、誰にでも起こり得るもの。しかも、仕事と両立するには会社の理解や制度がとても大切です。
2025年4月からは、「介護に関する雇用環境整備」が義務になりました。
これは、「社員が介護に関する制度を使いやすくするための取り組みを、企業としてひとつは必ず実施してくださいね」という内容です。
介護支援の取り組み、何をすればいいの?
次の4つのうち、いずれか1つを行えばまずはOKです。
① 研修の実施
介護に関する制度を周知するための研修を実施すること。
できれば全社員を対象に。少なくとも管理職は受講を。
動画研修でもOKですが、「受講したことが確認できる」形にする必要があります。
② 相談体制の整備
「誰に相談すればいいか分からない…」を防ぐために、相談窓口を設置しましょう。
メールや社内掲示などで周知し、対応できる体制を整えておくのがポイントです。
③ 利用事例の紹介
実際に制度を使った社員の声や事例を紹介することで、「うちの会社にも制度があるんだ」「自分も使っていいんだ」と思えるようになります。
職種や性別が偏らないよう、さまざまな事例を集めるのが理想です。
④ 利用促進のメッセージ発信
「介護と仕事の両立を応援しています」と、会社としての姿勢を表すだけでも、大きな支えになります。
社内報やイントラネットなどで、方針を伝えてみましょう。
制度は「使える雰囲気」が大事
介護支援の制度には、次のようなものがあります(要介護状態の対象家族を介護する場合)
- 介護休業(対象家族1人につき、最大93日まで取得可能。3回に分割して取得できる)
- 介護休暇(対象家族1人の場合、年5日まで。2人以上の場合は10日まで。時間単位の取得も可)
- 時間外・所定外・深夜業の制限(申し出ることにより)
- 短時間勤務制度(対象家族1人につき、利用開始から3年の間で2回まで) など
「うちにはまだ該当者がいないから…」と思いがちですが、介護は突然始まります。
いざという時、従業員が安心して制度を使えるよう、今のうちから整えておくことが、介護離職を防ぐ第一歩です。
最後に
人事労務の担当者は、幅広く業務を兼務されていることが多いと思います。
育児介護関連は法改正が多く、「何から手をつければいい?」という不安が出てくるのも当然のことです。
まずは、できるところから1つずつ。
雇用環境の整備であれば、相談窓口の設置・周知など、シンプルな形から始めてみませんか?
ご不明な点やサポートが必要なときは、社労士としてお手伝いしますので、いつでもご相談ください。