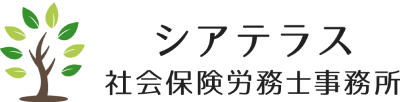2025年4月から、介護休業制度を利用する際の判断基準に見直しがありました。
「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」。この見直しについてお伝えします。
介護休業は、対象家族の年齢に関わらず利用できる制度。
ただ、障害や日常的な医療ケアを必要とするお子さんなどの場合には、これまでの基準で十分に対応できていませんでした。
介護休業の対象家族
対象家族:配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母
同居の有無:問わない
要介護状態
2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態のことを指します。
この状態がどういうことか判断するために、厚労省が判断基準を決めています。
要介護状態と判断できるのは、以下のいずれか。
- 介護保険制度で要介護2以上であること
- 介護を必要とする状態に関する判断基準に当たる場合
介護保険制度は40歳以上が対象で、40歳~65歳までは特定疾病が対象。
同制度に該当しない場合や、若い方の場合は、「判断基準」を利用します。
今回の見直し(判断基準への記載追加)
今回の見直しで「判断基準」のなかに、「障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む」旨が明記されました。https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/002140717.pdf
判断基準は、「水分・食事摂取」「衣類の着脱」など、12項目に分かれています。
各項目は3つに区分(例「水分・食事摂取」 1:自分で可、2:一部介助、見守り等が必要、3:全面介助が必要)。
要介護状態とは、2が2つ以上、または3が1つ以上該当、かつその状態が続く場合となります。
今回、「2:見守り」に、障害児・者の場合に必要な行為の「確認」「指示」「声かけ」等が含まれることが明記。
生活行動に対する支援の有無が、重要視される形となっています。
要介護状態と判断されれば、介護休業以外の両立支援制度(介護休暇制度、時間外労働の制限等)も対象です。
介護と聞くと、つい高齢の親世代を思い浮かべてしまいますが、
障害や病気を抱えるお子さんを支えるご家庭にとっても、大切な支援です。
今回の見直し、就業規則改正には当たりませんが、実務的には大切なポイント。
どうぞご留意ください。